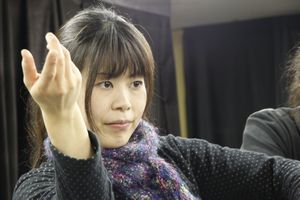14/01/20
『声無き声』
今回の『ドン・ジュアン』の出番に、私のセリフはない。
今公演の中で一番の若手だからね。そこからだよね。
そう考えてしまうだろう。
どっこい、どっこい。
セリフもなく、ト書きに動きも提示されず、最悪居なくても成立してしまう役を、いかに効果的に存在させるのか?
とある先輩には、一番難しいかもしれないと言われた。
自分を存在させるにはどうしよう…?
そのシーンで強調させるべき事は、強調させねばならない。
その上で、シーンに彩りをつける役どころになるのがベスト。
ふむふむ、そこをヒントに考えてみよう。
そして、最初の段階で、自分は道化、もしくは風景に色を増す為の存在なのだと思った。
これでは演出に怒られるであろう・・・という事をあえてやってみたつもりだが、いずれも中途半端。
やがて、ネタ重視になりすぎ、目指すべき場所に繋がらなくては意味が無いと気付く、という、魔の迷宮スパイラルに突入。
しかも、そんなスパイラルな中、肝心な《四畳半》ルールの中で、それを成立させなければいけない、という棒高跳び並のハードルが出現する。
やがて、要領の悪い考え方をしたばかりに、肝心な事を感じていなかった事に気づかされる。
その役として「その場」に居ること。
例えば、学生時代。
女子はグループをつくる。
気が合うからか、そうでなかは別にして、まるで義務の様にグループを作る。
私はもの心がついた頃から、そのグループ制が苦手であった。
「その場」にいる感覚も得られない上面な世界で、自分はどう存在すべきなのかを探る「居場所」を感じられない毎日。
辟易した。
このように、日常生活然り「居場所」を持った人と、そうでない人とでは、居易さと影響力は違う。
人間関係も然り、「その場」にいるべき人間でいなければならない。
それは「リアル系」の演劇然り、《四畳半》であってもだ。
このままで、ほぼ初挑戦となる《四畳半》で、自分の「居場所」を獲得しなければ。
セリフがなきゃ、「居場所」は無いのかい?
違う。
チャップリンやバスター・キートンも見尽くしてネタを探したが、大切なのは、ネタじゃない。
どんな魂で存在するか、なのだ。
その魂を、いかに明確に見せるのか、なのだ。
声を発する事が原動力で演劇の世界に入った私が、
声を出さずに自分をアピールする。
声無き声で、与えられたその場所で、緻密に叫ぶしかない。
このトライアルは、一見地味だが、過程は気が遠くなる程に壮絶なのです。
辻川ちかよ