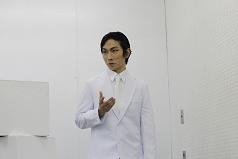13/03/25
「ひかりごけ」稽古場日誌/「モノサシ」
劇中にこんなセリフがある。
「食べちまう葬式[とむれえ]ってえのは、あっかなあ。」
八蔵が、死んだ五助を食べるか食べないかでもめているときに言うセリフ。
このセリフを質問と捉えるなら、答えは「ある」である。
世の中には、死んだ者を食べる文化を持つ民族がいる。
焼いたり、土に埋めたりせず、生きている人間の体に取り込む(食べる)ことで、死者が寂しくないようにするんだそうだ。
私たちが知っている葬式とは、全く違う。
話は変わるが、外国へ行くと、あいさつの際ホッペを合わせたり、抱き合ったりする。
だいぶ慣れたが、やはりまだまだ抵抗を感じる。
初めて会った人と、ホッペをくっつけるなんて、そりゃないだろ。
長年一緒にいる劇団員や家族間でも、そんなのしないぜ。
私の捉えている常識・非常識は、国や時代、法律、倫理観、道徳観、正義感が変われば、常識は非常識で、非常識は常識になる。
モノサシが変わるってことだ。
モノサシが変わることは分かっているけれど、肌感覚で捉えているモノは、なかなかそんなに割り切れない。
普段は頭でしか捉えていなかったことを、感覚で教えてくれるのが、「ひかりごけ」なんだなと思う。
そして、それを演劇にすることで、もっと敏感に伝えようとしているんだなと。
私たちは、時々、自分たちの常識・非常識と捉えていたものに、溺れそうになる。
自分たちのいる位置を、時々客観的に見ることが必要なんだろう。
そんな演劇、見に来てくださいませ。
小笠原くみこ
********************
山の手事情社公演「ひかりごけ」
詳細は、こちらからどうぞ。
********************