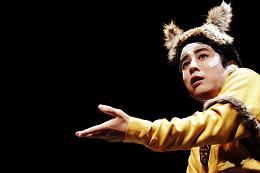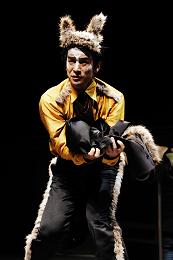13/03/02
「ひかりごけ」稽古場日誌/「次のステージへ」
只今稽古場では3月公演の「ひかりごけ」を制作中です。
発声後、《四畳半》の稽古をしてから台本稽古に臨んでいます。
《四畳半》は山の手事情社の演技スタイルですが、今回この《四畳半》を次のステージに上げるのが課題になっています。
10数年間付き合ってきたこの《四畳半》。
当初は新鮮かつ違和感があったモノが、今では当たり前に身体に馴染んでいます。
しかしこの当たり前が手強い。
何故ならやり慣れてそこに生理的に負荷が生じない。
いつもの身体だから思いがけない感情が出ない。
このままじゃつまらんぞ俺。
「いやいやそもそも"やり慣れている"というのが勘違いなんだ、もっと先があるハズだ」
そしてそれは劇団員と の関係性にもあらわれている。
付き合いの長い劇団員とは阿吽の呼吸で気を合わすことが出来る。
しかし初めて対峙した時はもっと相手を「見て」いたハズだ。ドキドキして。
いつの間にか相手のイメージを限定してしまっている。
それはマンネリに繋がる。
自分の中に揺らぎをつくり、常に緊張感のある関係で対峙しなければ。
と毎回男優4人が《四畳半》の可能性について実践と考察を繰り返しています。
言葉で説明出来ないモノへ昇華するつもりで。
つまり劇場でしか見れないものへ。
川村岳
※写真は、前回公演『トロイラスとクレシダ』から。
********************
山の手事情社公演「ひかりごけ」
詳細は、こちらからどうぞ。
********************