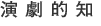歴史を味わう視点
身体を味わう視点を手に入れるために私たちが通常取っている方法を簡単に紹介しよう。様々な方法があるが、たとえば以下のようなものである。
トレーニング 1
今朝靴下と靴をどのように履いたか正確に再現する。それを靴下や靴を実際には用いないでおこなう。 これは一般のワークショップだけでなく俳優のトレーニングとしても実施している。指先の動きは思い出したとして、ひじがどのように動いたか、肩や首はそれにどう影響されたか。それらを検証することによって、靴下や靴を履く行為が実は全身を使って行なわれていることに気づく。さらにその時視線の先にあったものや、耳に入ってきた物音、よぎった考えなどもできるだけ正確に記憶をたどってみる。日常的な動作は習慣化しすぎてほとんど意識されなくなっているが、こうした単純なトレーニングを通じて自分の身体を内部から見つめる視線が獲得されていくことになる。身体との対話が始まるのである。
なかに時折、立てひざで靴下を履く人がいる。おそらく足袋の履き方だと思われる。家でそのようにしつけられたという人が多い。一見奇異な印象を持つこの履き方はしかし、戦前までおそらくどの家庭でも見られたごくあたり前のしぐさなのではないだろうか。それに思い至る時、私たちの失ったものの大きさに愕然とする。和服には正しい着付けの方法がある。正しいものだけでなく、粋な方法もある。靴下や靴は西欧から入って来た衣服習慣なのだからそのスタイルに準ずるべきなのかもしれない。が、私たちが暮らしている家屋にはフローリングもあり畳もある。生活習慣が西欧化しているとはいえ、西欧とは違う。その家屋で正月もクリスマスも迎えるのである。畳敷きの座敷で靴下を履く私たちに、それに即したスタイルが果たしてあるのだろうか。私たちとは一体何ものなのか。
それはたとえば「ハムレット」は知っているのに、能の謡曲となると知るものが少ない、そのように偏った演劇的知識を持つ日本人にグローバリズムを説く資格があるのかという問題とも関連する。自分の先祖の業績や足跡には無頓着でありながら、西欧の文化にはときに狂奔に近い反応を示すわが国の文化状況もまたうぶな部分を広くのこしていると言わねばなるまい。オペラもバレエもすばらしいと思うが、その知識や興味だけが突出しているのは、自分の家族のことは知らないのに、遠く離れた他人の家族の内情に詳しい人間のように、他国から見ると不気味に映るのではないだろうか。しぐさと美学の結びつきを考えるとき、演劇の果たす役割は決して小さくない。私たちは日常のしぐさに美学が存在していたことさえ忘れている。演劇にはその時代のしぐさを昇華し抽象化し美学化する役割があることは演劇にまつわる教養、すなわち「演劇的知」として認識されるべきだろう。日本とは、日本人とは何ものなのか、つまり私たちとは何ものかを考える上で多くのきっかけを演劇は持っている。しぐさだけでなく、日本語の語り方もまた現代演劇が取り組まなければならない課題の一つである。正しい、つまり美しい日本語の語り方を見つけ、それを磨き、継承していく作業は他のどの芸術分野が担うものでもなく演劇が担うべき範疇である。 世阿弥は、「風姿花伝」という世界で最初の体系的な演技論を書いた私たち演劇人の偉大な先達である。その世阿弥が完成したといわれる能にしても、室町時代の人々がその舞台で謡われるように語り合っていたわけではない。江戸時代に完成をみた歌舞伎や文楽における義太夫にしてもそうであろう。それでいて、室町時代、江戸時代というものを私たちが記憶する時、そうした様式抜きに考えることはできない。おそらく他国の人々が日本人というものを記憶する際にもこれらの様式は濃厚な影響を持っているに違いない。演劇とは、あるいは演劇の様式とは記録ではなく、記憶の形態であると私は考える。このように、ときとして演劇は、特にそのすぐれた表現形態となったときに、私たちの日常や暮らしを歴史の中の一点として味わう視点を与えてくれるのではないだろうか。観客がそれらのことに意識を置いていれば、それは必ず作品に反映する。「演劇的知」が演劇人を育てるというのことの一つの証左と言えよう。