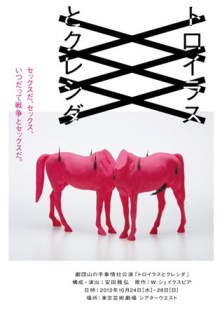12/09/12
ギリシア人の戦闘
映画で観るようなキチンと縦横に編隊を組んで戦うファランクス(密集方陣)という陣形はもう少し後に生まれた戦い方で、「詞戦い(ことばたたかい)」という相手を挑発して一騎打ちを挑む戦い方が主流であった。
そして、あくまでも敵味方入り乱れた混戦状態での戦闘であった。
戦闘の手順はまず長距離では弓を射かける。
中距離まで近づくと槍を投げたり、突いたりした。
槍には「ドリュ」と呼ばれる約2mぐらいのものと、「エグコス」と呼ばれる5mにも達する長槍があった。
そして、その槍が使えなくなると木の葉型の「クシポス」という剣で応戦した。
剣がなければ掴みあい、殴りあいである。
「デンドラの鎧」という頑丈な鎧もあったが、全身青銅製で大変重く動きづらいので、戦闘に不向きであった。
当時ギリシアには製鉄技術がなく、もっぱら青銅を使用していた。
青銅は高価なため一部の有力者しか持っていなかったとされている。
当時、武器や防具は自費だったため下級兵になればなるほど裸に近い装備だったようである。
そのため敵兵を殺したときは隙さえあれば武器や防具を奪って自分の物にしていた。
当時は英雄の死を悼むために休戦したり、冬の寒い時期は戦わなかったり、忌引きや冬休みのような習慣もあったようである。
戦争は主に暑い季節がメインだったのだろうと推測できる。
現代の発掘調査でギリシアは土葬が主流だったようであるが、遠隔地で戦うギリシア兵たちが敵国の土地で土葬できたかどうか。
海に流すか火葬にしたかも知れない。