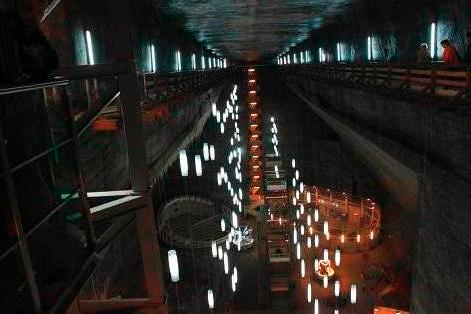11/06/30
三年目のルーマニア
三回目のルーマニア公演。
今年も反応としては上々で、成功裡に終わったと思います。
とくにトゥルダという町での公演はあまりに拍手が盛大で驚きました。
とても小さな町で、日本人が公演するのは初めてということでしたが、
それにしてもシーンが終わるたびの拍手、まるで大衆演劇のようです。
毎年ルーマニアの観客には想像以上の熱い視線と拍手をいただいてきましたが、
ここまで大きな拍手をもらうと逆に戸惑いますね。
拍手はとてもうれしいのですが、
一方で単なる物語や《四畳半》の物珍しさに対しての賛辞が大きいのではないかなと思ってしまうのです。
どこまでグッときてくれているのかなあと。
近松独特のストーリー展開は面白いはずだし、恋の情念も世界共通でしょうから、
それが伝わったんだったらいいじゃんという一面もあるのですが、
日本人である僕らがこういう舞台表現にたどりつくしかなかった背景みたいなもの、
美学みたいな(僕らにもはっきりと言葉にしにくい)ものは決して理解し合えないんだろうなと思います。
もちろん理解し合う必要なんてないし、
むしろ「違う」ということがわかることが一番大事だと思うのですが、
その「違う」ということがはっきり伝わってないのではないかと思ってしまうのです。
近松の物語に共感して「同じだ!」「わかるわかる!」と思われているような。
演劇はスポーツのように世界共通の同じ土俵でやりあうものではないんだと思います。
価値観を共有するんじゃなくて、違う価値観がぶつかる場所というか・・。
100年以上前にヨーロッパ公演をした川上音二郎も、
日本人の舞台を初めてみる外国人には大ウケだったと思いますが(よく知らないけど)、
嬉しさ半分、どこかでそんなことを考えていたんじゃないでしょうか。
それにしても日本からルーマニア・シヴィウまで飛行機とバスで24時間。
クタクタになったとはいえ、やはり丸一日で地球の裏側に行けてしまうお手軽さ。
今は当たり前ですが、いろいろ失ってきたものもあるんでしょう。
100年前であれば、船で数か月、世界中の町に停泊しながらおそらく一生の何分の一かの経験が出来たであろう
特別の旅だったと思います。
川上音二郎一座は一体どれだけの苦難と特別な経験の果てに、どれだけ緊張しながら外人の前で舞台に立ったんでしょう。
そんなことをちょっと考えてしまいます。
《オッペケペー》と《四畳半》、比べても仕方ないですが、ちょっとした妄想です。
毎年温かく迎えてくれるルーマニアの人々に感謝しつつも、早くもツアーに慣れ始めている我々。
これからも外国の観客との出会いをホントに奇跡的な出来事として噛みしめていかないといけないなと思います。
山本芳郎